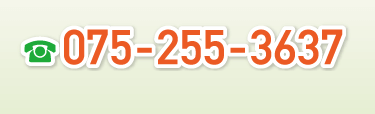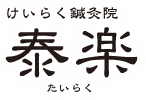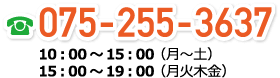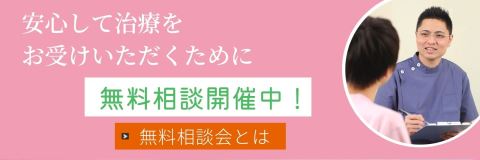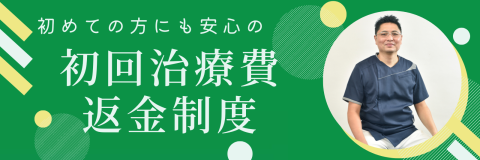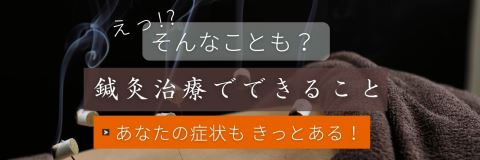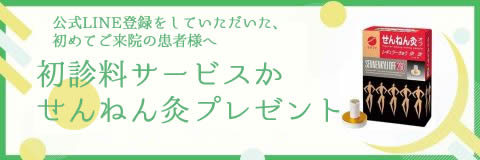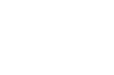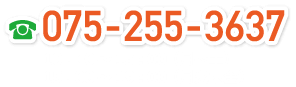膝痛
「正座ができない?」
「階段で痛む?」
「湿布だけ貼っているけどなんだか気休めにしかなっていない」
少しでも日常生活のできないを解消しませんか?
まずは、膝痛の原因をしっかりと突き止める
膝に関わらず整形外科的疾患の原因には、大きくわけて障害と外傷があります。
障害と言うものは、いわゆるオーバーユースや加齢に伴う膝の病変です。
外傷と言うものは、スポーツや不慮の事故などで怪我をした時の病変です。
ですが、膝に関しては、障害でも外傷でも同じような症状が現れます。
その為、しっかりと痛みの原因を突き止めた上での治療が症状改善の近道となります。
主な膝関節の病変は、下記のようなものがあります。
前・後十字靭帯損傷
内・外側副靭帯損傷
内・外半月板損傷
膝関節を構成する骨の軟部組織損傷
膝関節を構成する骨の変形
このような病変をしっかりと見据えると治療効果も上がりやすくなります。
体重の管理は、膝痛を軽減するカギです。
膝には、体重の2~3倍の力が加わっている。
日常生活をしているだけで、膝への負担は、実は大きいんです。
少しシミュレーションをしてみましょう。
体重50kgの人の場合
歩行時にかかる膝への負担→150kg(体重の約3倍)
階段を上る時の膝への負担→200kg(体重の約4倍)
階段を下る時の膝への負担→350kg(体重の約7倍)
体重55kgの人の場合
歩行時にかかる膝への負担→165kg(体重の約3倍)
階段を上る時の膝への負担→220kg(体重の約4倍)
階段を下る時の膝への負担→385kg(体重の約7倍)
歩く時、階段を使う時、様々なシーンで、体重が5㎏増加するとおよそ10%負担が増えるということがわかります。
逆に言うと、5㎏減らせば10%負担が減るということです。
体重の増減で膝の症状は、激変します。
BMIの計算方法で25を超えているようでしたら、22くらいを目標に体重コントロールをしていただくと、よいと考えています。
BMI計算式 体重(㎏)÷身長(m)×身長(m)
筋力低下は、できる限り避ける。
膝が痛いですが、運動をした方がいいですか?
患者様からよく質問を受ける内容です。
答えとしては、“YES”とも“NO”とも言えます。
基本的には、運動ほどの強度でなくても、動いてもらうことは重要です。
筋肉の強化や減少抑制による関節の安定感をだす、関節の可動域を大きく動かすことによって腱や靭帯の柔軟性を取り戻す、カロリー消費による体重減少などプラスに働く要素が多いからです。
ただし、急性期の疾患や関節が曲がらないほど腫れてるというものに関しては、安静の方がよい場合も多くありますので、やみくもに動くと言うのは、注意が必要です。
膝の水は、冷やしたいという体の反応。
膝に溜まった水は、抜かない方がイイ?
これも患者様からよく質問を受けます。
鍼灸師としては、人体が生理的反応として膝に水を貯めてたのなら、冷やす必要があるから溜まったと判断して、抜かないようにしてほしいというのが考えです。
ですが、整形外科でも溜まった水を抜きっぱなしと言うケースは少なくなってきているようですので、日常生活に支障が出るレベルで水が溜まっている時は、抜いてもらうことを選択肢に入れてもいいと思います。
患者様のQOL(生活の質)を上げるための最善の手段をとることが、最も望ましいことと考えています。
よく水を抜いたら癖になるなんてことを言いますが、炎症があるのに冷える成分の水を抜いたら、それはすぐに溜まってきます。
ですが、抜くと同時に消炎処置もおこなっていると徐々に溜まりにくくなってきます。
そういった場合は、安静が基本スタイルになると思います。
膝痛の鍼灸治療でサポートする事。
お灸をすることで患部が温まります。
温まると、筋肉が動きやすくなり患部の動きがよくなります。
さらに、血液循環もよくなりますので、痛み除去に役に立ちます。
また鍼をすることで、関連する筋肉を軟らかくし、関節にかかる負担を軽減し、痛みの増悪に対して役に立ちます。
もちろん、鍼をすることで血液循環も改善しますので痛み除去に役に立つことは言うまでもありません。
整形外科で湿布だけの処置しかない方はぜひ鍼灸治療を試してみてください。
生活しやすいお体を一緒に作っていきましょう。
関連記事
治療期間の目安 体重など膝への負担がどの程度かを見き分けてからの判断となる場合が多く、症状を確認してからご提案。
治療ペースの目安 2~3日/回(初めの3回程度) → 2~4週間/回(保存治療時)